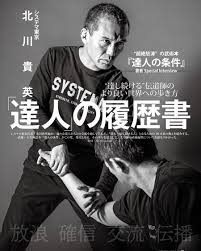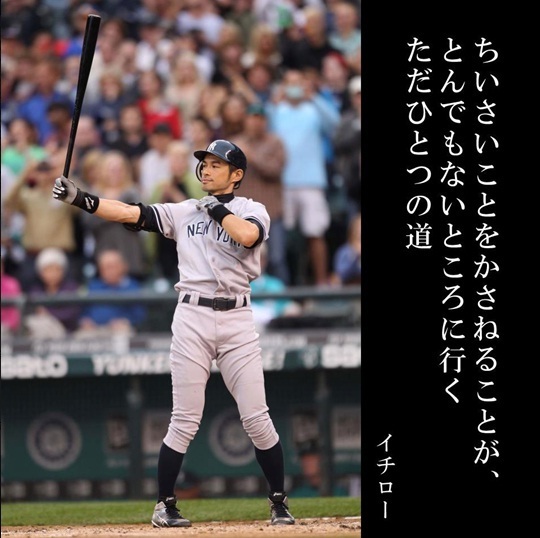※本記事には卓球の解説文中に一部広告文を掲載しています。
日本の卓球人気は根強いものがありますね。
オリンピックでも世界大会やアジア大会でも、日本の卓球選手が活躍する場面も多くなっています。
卓球は子供の頃から馴染み深く、昭和の頃はあちこちに卓球場も存在していました。
温泉地に行けば浴衣姿で楽しむ「温泉卓球」が人気でした。
ここでは卓球というメジャーなスポーツについて、初心者が上手くなる方法やコツをお伝えします。
卓球の歴史と現在
卓球の歴史をひも解くと、インドやフランスの娯楽や遊戯が起源となっています。
卓球発祥の国はイギリスとなっていますが、その歴史はまだ浅く起源は1880年代と言われています。
1900年代になって第一回世界選手権がロンドンで開催されたのが初の国際大会です。
さらにオリンピックの競技として初めて登録されたのは、1988年のソウルオリンピックからです。
以降オリンピック競技として、必ず登録されるほどの人気競技となって世界から愛されるスポーツとなりました。
日本でも卓球は昔から根強い人気があり、2024年に行われたパリ五輪でも注目が集まりました。
この大会では、女子と男子で大きく明暗が分かれる結果となったことも覚えている方も多いと思います。
女子チームは輝かしい成果を挙げた一方で、男子チームは残念ながら多くの課題を残すオリンピックとなりました。
まず女子シングルスでは、早田ひな選手が怪我に苦しみながらも銅メダルを獲得。
その思いが他のメンバーにも伝わり、団体戦も勢いづき平野美宇選手、張本美和選手と挑んだ女子団体戦では、
決勝で中国には敗れたものの、銀メダルを獲得しました。

東京オリンピックでもそうでしたが日本女子卓球が、
世界のトップレベルであることが証明されたパリオリンピックとなりました。
反面、男子シングルスでは、期待された張本智和選手がベスト8止まりとなり、
男子団体戦でも、準決勝でランク下のスウェーデンに敗れ、
さらに3位決定戦ではフランスに惜敗してしまいました。
しかし、男子はその屈辱を晴らすべくその後の国際大会で見事な復活を遂げたのです。
張本智和選手は、2024年10月のアジア選手権においてシングルス金メダルを獲得。
次いで行われた11月のWTTファイナルズ(福岡で開催)では準優勝となり、
世界ランキングも3位へと返り咲くことが出来ました。
また、戸上隼輔選手と篠塚大登選手の男子ペアによるダブルスでも、
WTTファイナルズで準優勝に輝くなど、男子選手たちはその後確実な前進を遂げています。
さらにさらに若手選手の台頭もあり、2024年以降は多くの若手選手たちが、
卓球界を大いに盛り上げてくれました。
なかでも、注目を集めたのが16歳の張本美和選手です。
また、彼女だけにとどまらず、大藤沙月選手、松島輝空選手らも台頭してきて、
2025年以降も世界で期待できる若手選手が数多く生まれたのです。
卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
卓球はサーブとレシーブで勝負する競技
ご存じのように卓球という競技は、サーブとレシーブで勝負します。
特にサーブは様々な変化をつけて、相手のレシーブのミスを誘発させることで、
得点につなげるケースが多いのですね。
卓球の攻撃の優位性は、まずはサーブにあるといっても過言ではありません。
国際大会の代表同士のハイレベルな試合でも、サーブのみで点を取るシーンがよくあります。
つまり、サーブのレベルが高いほどそれだけで強い武器になるのが「卓球のサーブ」なのです。
サーブを得意とする選手は、卓球選手として必ずレベルアップできると言っても良いでしょう。
強いサーブのメリット
卓球のサーブの重要性をお伝えしましたが、サーブが上手いとどんなメリットがあるか?
具体的には以下3つのメリットが挙げられます。
1、試合の流れを引き寄せることができ、先手を取りやすくなる。
ご存じのように卓球においてサーブは1球目の攻撃です。
そのサーブが強力であればあるほど、相手のレシーブが甘くなりやすく、
先手が取りやすいのですね。。
2、いろいろな大会や試合に勝つ回数が増える。
サーブが上手いと、大会などで初顔合わせの相手に大きなプレッシャーを掛けることができます。
相手選手に強いサーブで動揺させると、1つの強いサーブだけで試合に勝てる要素が生まれます。
特に、相手が初心者や中級者以下の選手であれば、サーブだけで試合に勝てる可能性があります。
3、強敵であっても惨敗することがなくなる。
卓球における試合形式では、サーブは必ず2本交代となっています。
ですからその2本のサーブで自分の試合展開や流れをを作りやすくなります。
強いサーブによって、強敵にも通用するテクニックがあれば、
自分のサーブ2本での得点確率は飛躍的に高まっていきます。
つまりたとえ強敵であっても、連続失点せずに食らいつくことができるというこです。
当然勝つチャンスも出てくるはずです。

卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
卓球のサーブの重要性と練習方法
では、卓球におけるサーブが上手くなるポイントや練習方法のコツなどを紹介します。
まずサーブにおいて「4つの重要ポイント」をお伝えします。
卓球のサーブの4つの重要ポイント
・回転・コース・速さ(スピード)・高さと長さ
この4つが強力なサーブの大きな要素となりますので、それぞれを具体的にお伝えします。
1、回転の重要性
卓球のピンポン球は軽いがゆえに、いろいろな回転が掛けやすいのですが、
サーブにおける回転は以下4つに分けられます。
・下回転・上回転・横回転(右、左)・ナックル回転(無回転)
こういった回転を単純に使い分けるだけでなく、それぞれ組み合わせて使うサーブが有効になります。
横回転と下回転で横下回転と呼ぶサーブもありますが、
回転の掛け方はラケットの持ち方を変えたり、打ち方を変えたりして、
大きな変化球や小さな変化球にする場合もあります。
どちらも鋭く変化させることで、相手のレシーブを乱すことになり、
回転の重要性が理解できると思います。
2、打球のコースの重要性
卓球の試合においてまず知るべきポイントは、
「相手が苦手とするコースはどこか?」
です。
これをを見抜くことができれば、試合を有利に運べるのです。
卓球において打球のコースを、大きく3つに分けることができます。
・フォア・ミドル・バック
フォアは相手のラケット側のコースで、バックはその反対側のコースです。
ミドルはフォアハンドとバックハンドの間を指し、卓球台の真ん中付近のことです。
相手のレシーブを見て、相手選手が嫌がるコースを見抜くことが重要になります。
卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
3、打つ打球の距離(短さ・長さ)
卓球の打球の長さ(ロングボール)もまた大変重要なポイントです。
相手選手が台に近い位置にいる場合は長い打球が有効になり、
逆に台から遠い位置に立った場合は、短い打球(ショートボール)が有効になります。
ただそし、ワンバウンド後に台から出るようなロングボールやサーブは、
ドライブなどで攻められやすくなりますが相手のミスも出やすくなります。
また、ショートボールでツーバウンド目が台を出るか出ないか、
ギリギリの長さを打てるようになると、相手の判断ミスを誘えますし、
返されても甘いボールになりやすく、ここでチャンスも生まれます。
サーブ打球の長さが中途半端になると、逆に攻められてしまうことも多くなるので、
自由自在に長さを打ち分けられるようになれば、レベルアップが期待できます。
4、打つ打球の速さとトスの高さ
ここでいう速さとは当然打球速度ですが、高さとは打球の高さではなく、
サーブを打つ直前の「トスの高さ」です。
トスを高くすればするほどボールの落下速度は速くなり、
そのため相手選手にサーブの打球の瞬間が見えづらくなります。
さらに、打球速度も上がります。
ただし高いトスは、サーブを打つ側もテクニックが必要になりますので、
これは何度も繰り返しサーブ練習するしかありません。
また、ここでさらに重要なことは相手選手との駆け引きです。
いくら高いトスから正確なサーブを打っても、相手が中級者以上のレベルですと、
トスの高さや打球速度は大した効果を生んでくれません。
大事なことは「相手選手の意表を付くこと」です。
一つの方法としては、例えば数回相手のバックハンドにサーブを打っておいて、
突然フォア側に長くて速いサーブを打つなどです。
その逆のやり方もあります。

卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
強力なサーブを覚えるためのコツ
卓球を始めて間もない初心者が、まず覚えるべきサーブをお伝えします。
卓球においてサーブの重要性は前述した通りですが、相手に簡単に打ち返されないための、
覚えておくべきサーブと、身につければ試合に勝ちやすいサーブをお伝えします。
下回転サーブを覚えよう
球に下回転をかけたサーブは、相手選手に最も攻められにくいサーブの一つです。
下回転がかかったサーブを普通に打ち返すと、ほとんどの場合ネットにかかってしまいます。
ですからした回転のかかったサーブを、ネットにかからず打ち返そうとすると、
打球が高くなりやすく、甘い球が返ってきます。
その甘い返球を狙って、スマッシュ気味に攻めて行くのが一般的な攻め方と言われています。
下回転サーブを打つコツは、トスした球の一番下部に当ててからラケットのラバーの端から端まで、
ボールを転がす感じで打つことです。
イメージとしては、球をカットするように素早くラケットを振り抜くことです。
何度も練習すれば強力な下回転がかかり、有効なサーブになるはずです。
フォア・ロングサーブは決まりやすい
フォア・ロングサーブとは相手選手のフォア側に、長く速いサーブを打つサーブです。
このサーブを突然打たれると相手選手は追いつけなかったり、返球で精一杯になったりします。
フォア・ロングサーブの一番のコツは、テクニック以前に相手選手に打つことを気づかせないことです。
サーブを打つ前の体勢を小さくしつつ、いかにもカットボールなどを打つポーズから、
いきなりフォア・ロングサーブにすると、相手選手に有効なサーブになることが多いです。
特に初心者や中級レベル程度の選手が相手なら、フォアに長くて速いサーブを打てるようになると、
非常に有利に試合を運べます。
卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
ナックルサーブは強力な武器
野球の投手が投げる変化球に、ナックルボールがありますが、
卓球でいうところのナックルサーブとは無回転サーブのことです。
ナックルサーブの打ち方は、下回転サーブと同じフォームで打つのがポイントです。
サーブを打つ瞬間は下回転サーブと違い、球をラケットに擦らせるのではなく、
ラケットの一点に当てて打つことです。
相手選手は下回転がかかったサーブと思いレシーブすると、
ほとんどの場合、打ち返した球は浮いてしまいます。
ですから、こちらにとっては返しやすい甘い球になりますので、
ここでスマッシュを決められます。
下回転サーブに見せかけたナックルサーブは、初心者だけでなく中級レベルの相手にも大変有効なサーブです。

試合に勝つためのサーブの練習方法
卓球のサーブは多ければ多いほど試合に有利ですし、相手選手にプレッシャーをかけることができます。
ですからより強力なサーブが多く打てるように練習するのが大切なことです。
サーブ練習の流れとしては、いろいろなやり方がありますが、
基本として以下のような方法を取り入れてみてください。
いろいろなサーブのフォームを身につける
今のご時世は卓球のプロや優秀な選手の動画が数多くアップされています。
そういったプロ選手の動画や映像を繰り返し見て、正しいサーブのフォームを頭に入れることです。
サーブは回転の掛け方が重要とお伝えしましたが、相手選手にとってどんな回転のサーブか、
わかりづらいフォームを覚えることが重要です。
特にトスの高さからラケットの動き、そして打つ瞬間の体勢をしっかり目に焼き付けましょう。
打ち方の微妙な動きの違いを見抜けるようになれば、あとはそれを取り入れて練習するだけです。
一人で出来るサーブ練習を根気よく
先ほどお伝えしたプロ選手のサーブのイメージを頭に入れて、
次は実際にひたすら数多くサーブを打つ練習を取り入れてください。
ダラダラ打つのではなく、一球ごとに試合本番をイメージして、
サーブを打ってください。
打球の高さ(ネットスレスレか)打球の入った位置、そして打球の強さを意識してください。
またその際に、サーブが上手くいったどうか以上に正しい(イメージ通りの)フォームで打てたか、
この点を重視してください。
卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
実戦形式での繰り返しサーブ練習をする
ある程度、ミスなくサーブが打てるようになったら練習相手との実戦形式でのサーブ練習です。
この時にポイントにしたいのは「サーブを相手コートに入れる」ことも大切ですが、
「相手にミスをさせられたか」あるいは「打ち返されても甘い返球になったか」
この点を重要視することが大事です。
サーブを入れても、上手いレシーブで反対に攻められているようでは試合では通用しません。
とにかく相手に強いレシーブを打たせないことを一番にサーブを打ち込むことです。
またサーブは打って終わりではなく、相手がレシーブすればラリーが続きます。
ですからサーブ後に、今度はこちらがレシーブするための動きを瞬時に整えることが重要です。
サーブ後の次の動きや、次の攻めも考えてサーブが打てるようになるように繰り返し練習してください。

試合に勝つためにレシーブが上手くなる練習方法
試合で勝てる強いサーブを覚えることが一番ですが、そうは言ってもすべてのサーブが決まることはありません。
ですから次に重要なことは、正確にレシーブするテクニックを身につけることです。
これもまた繰り返しの練習になりますが、基本的には二つのレシーブ方法しかありませんので、
根気よく取り組んでレシーブテクニックを磨くことです。
フォアハンドでレシーブ
オーソドックスなフォアハンドでのレシーブは、何よりも打球の強さを意識してください。
スマッシュとまではいかなくても「正確に強い打球を返せる」ように心がけてください。
またその場合、相手のどの位置に返すかも大きなポイントです。
ケースバイケースですがラリーが続いた場合、原則は「左右への打ち分け」です。
いつも同じ位置への打球では、相手選手も慣れてしまい逆にこちらに難しい球となって打ち返されてしまいかねません。
バックハンドでレシーブ
バックハンドもまた繰り返しの練習になりますが、フォアハンドと違い体勢がやや悪くなりやすいので、
ラケットがスムーズに動かせるように、「素振り練習」も重要になります。
フォアハンドと同じくらいにレシーブ出来るようになるためには、
練習相手に最初は緩いサーブを打ち続けてもらいます。
そして徐々に強いサーブにしてもらい、正確に打ち返せるように練習します。
こちらもまた、左右に打ち分けられるようになるまで根気よく取り組んでください。
卓球ジュニア選手育成プログラム ~試合で勝ちたいジュニア選手や親御様へ
ジュニア卓球に特化した指導法~【加藤雅也 監修】オンライン版
卓球のコントロールが上手くなるために
卓球の試合の場合、相手のコート(台)にどれだけ正確に打球を打ち込めるか?
それはもちろんサーブにもレシーブにも言えることです。
正確に打ち込めるためのコントロールはどのように身に付けられるか?
ここではコントロールをレベルアップするためのコツや練習方法をお伝えします。
ラケットの癖を知ること
卓球のラケットは、どのラケットでもいろいろな特徴や癖があります。
ラバーの特徴から始まり、握り部分の癖などさまざまです。
自分のラケットにどんな癖があるのか?
まずこれを知ることがコントロールを良くする第一歩です。
そしてその癖をしっかり掴むことで、どのようにラケットを振れば、
どこに打球が飛ぶかということを覚えていけます。
プロの卓球選手でも、いきなり他人のラケットで球を打っても、
失敗することが良くあります。
つまり自分のラケットの癖を知り尽くしているからこそ、他人のラケットでは、
最初は上手くコントロールできないということです。

ラケットに球を当てる位置を常に覚えておくこと
卓球経験者ならわかると思いますが、同じフォームで球を打っても、
ラケットの当てる位置で打球の高さや角度が全く違ってきます。
ですからまずは、基本である「ラケット中央(からやや上)に当てるテクニック」を、
徹底的に身につけてください。
これを身につけることで、基本のコントロールテクニックを体が覚えてくれます。
そして速い打球に対応するうちに、ラケットに当たる位置が微妙にずれてきます。
その時にラケットをやや被せて打ち返したり、手首を寝かせて打ったりするうちに、
どのように打ち返せばコントロール良く相手コートに入っていくか、
体が覚えてくれます。
これもまた繰り返しの練習で覚えていきますので、
焦らず根気よくコントロールを身につけてください。
手首を柔らかく使うことを覚えよう
卓球の初心者の場合、ラケットを握る手に力が入りすぎているケースが目立ちます。
必要以上に強く握ると、サーブでもレシーブでもコントロールが狂いやすくなります。
適切な握りで手首を柔らく使うことで、コントロールミスが減り、
狙った位置に打球を打つことが可能になります。
ラケットを軽く握った状態で素振りを繰り返し、力加減を覚えたら、
実際に球を打つ練習に切り替えてください。
手首を柔らかく使ったサーブやレシーブは、コントロールが良くなる秘訣です。
もちろんここ一番で決めるスマッシュなどは、多少握った手に力は入りますが、
スマッシュの速さは、力ではなくラケットを振る速度であることを忘れないでください。
卓球が上手くなる記事まとめ
卓球人気はますます熱を帯び始めていて、数年前に発足したTリーグの活況をみても、
卓球人口の増加が顕著であると言えます。
近年ではリーグ初となる、四国地方での試合が開催されました。
これまで公式戦が行われていなかった地方や地域での試合は、
多くの地元ファンを引き付けると同時に、卓球の魅力を伝えるきっかけとなっています。
そして卓球を始めた人たちが、少しでもレベルアップしたいと練習に取り組んでいます。
今回の記事はそういった人たちの参考になればと思い掲載させていただきました。
【お勧め記事】
バドミントン初心者が上手くなるコツや方法を教えます!基礎打ちが上手い人の練習メニューやバドの魅力も紹介
柔道が強くなるには?基本の練習方法はまずこれから!必要なトレーニングを教えます!柔道の魅力も紹介!